人はみな<今>を生きています。当たり前だけれど。ところが、人は<今>というものの豊さやかけがえなさを、ほんの少ししか受け止めることができません。だから過去を振り返って、「ああ、あのときは...」と感慨にふけったり、悔やんだりする。そして時を経てようやく、遠い過去になったかつての<今>の豊さに気づきます。
川端康成という大家の魅力は、そんな<今>のかけがえのなさを、現在進行形で的確にくみ取り、繊細な言葉で定着していくことで成り立っていると思います。それは並の感性でなせることとは思えません。
「古都」(新潮文庫)を読みながら、一言ひとこと綴られる今に引き込まれました。
<今>とは、些細な日常です。今を精一杯生きる...と言うけれど、難しい。ただ過ぎ去るに任せるのは簡単だけれど。たとえ日常を離れて名所旧跡を旅したって、「!」とか「感動〜」とか、一言で通り過ぎて翌日には忘れてしまう。SNSの投稿なら、まあ写真とかそこにくっ付けて。
そんな具合に、わたしたちは「ていたらく」だから、「古都」を読んではっとさせられるのです。きめ細かな自然への眼差し、人と人のふれあい、古い歴史を背景にした祭り。親に捨てられ、別れ別れだった姉妹の出会い。一つひとつ、<今>の美しさと哀しさをしっかり掬い取って描くことで物語は進みます。
この作品の主人公は、人ではなく、タイトル通り京都という歴史都市だと思いました。歴史に育まれた風土の<今>の中に登場人物たちがいて、彼女や彼らの行いは、花が咲いて散る永い古都の営みの一部のよう。
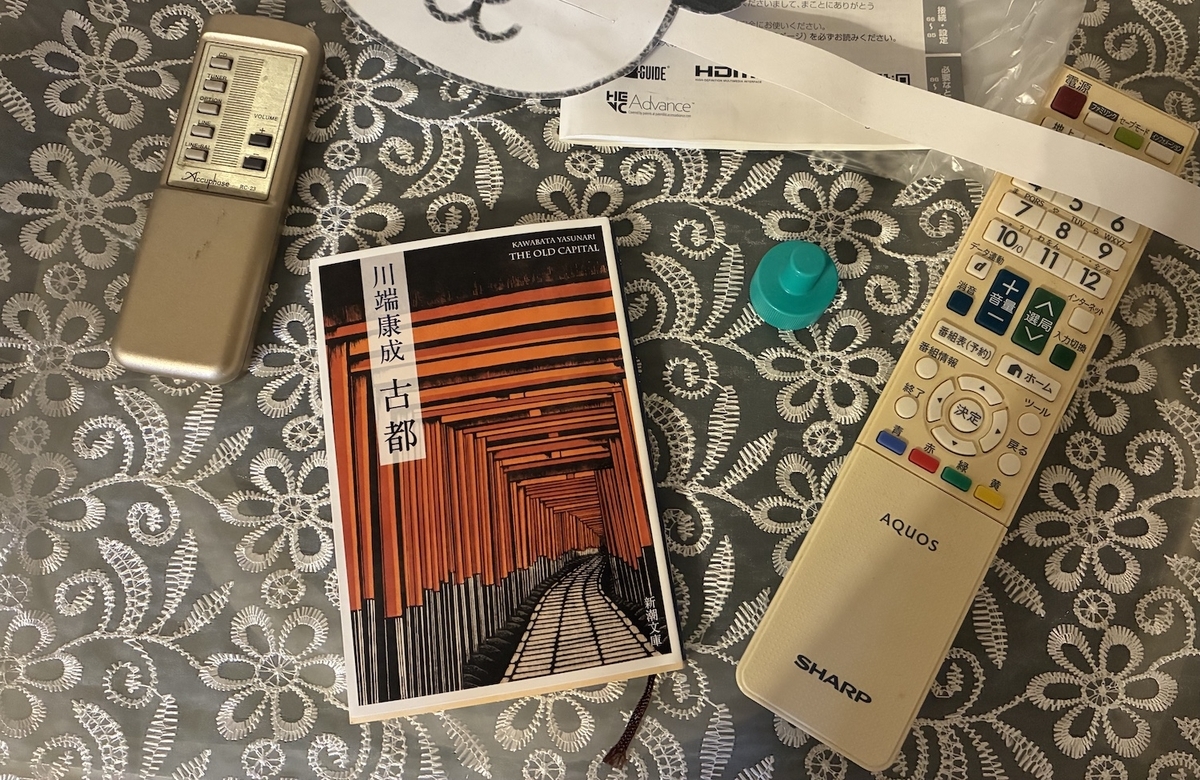
昭和36年から翌年1月まで朝日新聞に連載後、刊行された作品。「作者あとがき」で川端は、執筆中は眠り薬を乱用し、うつつないありさまで書いたと述懐しています。何を書いたか記憶が定かでないと。完成後、東大病院に入院しました。
「だからこれほど美しい作品を書けたのか」ーというのは、わたしの意地悪な感想かもしれません。平時に書いた川端の小説は、ときに妖艶で、今風の言葉を使えば「ヘンタイ」的でさえあります。現実を超えた幻の美を求めると、そうなるのでしょう(たぶん)。
そんな中にあって「古都」は、「伊豆の踊り子」と並んで、だれもが素直に喉を潤すことができる清流なのです。
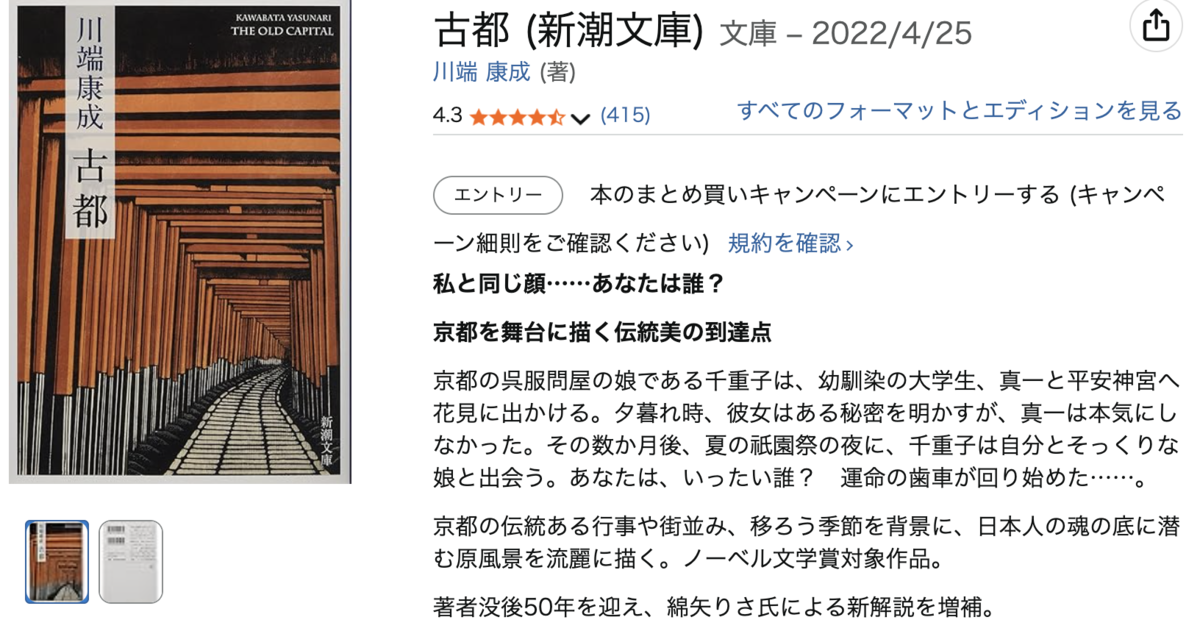 amazon
amazon
