これは評伝なのか、小説なのか。「イエスの生涯」(遠藤周作、新潮文庫)を読めば、だれもがそう思うでしょう。紀元前3年に生まれ、ナザレの町で貧しい大工として働き、短い生涯の晩年に弱きものへの愛を説き、33歳ごろ十字架の磔になって刑死したイエス・キリスト。
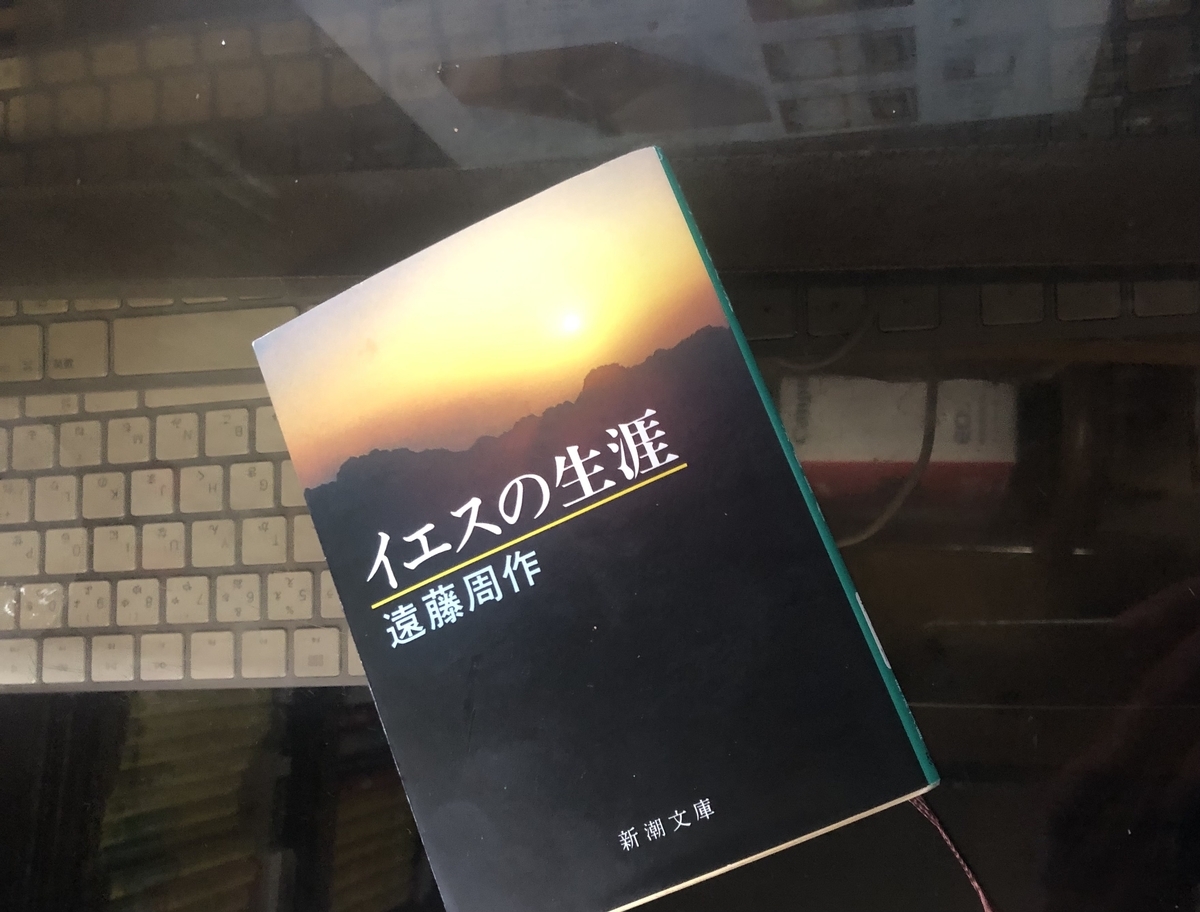
評伝であれば、イエスという神格化された存在を地上に引き戻し、一人の生身の男としてとらえなければ成立しません。
できる限り死までの事実や証言を調べ、真偽を確定する必要がありますが、ベースにできる史料は極めて限定的です。主に、イエスの死後に使徒がまとめた4つの福音書を中心とした新約聖書。しかし聖書には、「事実」と、「宗教的な真実」、もしくは後世の信者による願望が入り混じっていることは言うまでもありません。
必要となるのは、事実のみを推定し、現前させる想像力と論理的思考でしょう。この本は旧約、新約聖書の読み込みと過去のイエス研究を踏まえながら、当時のイスラエルとローマの政治的均衡やユダヤ教の動向、民衆史を背景にイエスの軌跡を描こうとした試みです。
子どものときにカトリックの洗礼を受け、生涯キリスト教徒だった遠藤周作は、20世紀の戦後日本に生きる作家でした。高度な科学技術と知見が浸透した社会で、キリスト教とは何かを問い続けることは必然でした。
作品の中で、イエスはどんな奇跡も起こせません。目が見えない者は見えるようになることを期待し、歩けない者は歩くことを望みます。しかしイエスは寄り添うだけで、現実的には無力です。期待が募るほど、無力は無惨な現実です。やがて民衆はイエスを侮蔑し始め、弟子たちは去っていきます。その果ての捕縛と十字架。
しかし、無力で無惨な最期だったからこそ、死後に信仰の対象になった。無力であることの深い力。この作品は、信仰を捨てられない現代作家の苦悩が生み出した、一つの帰結だと思います。
作者がイエスに向き合っているのに対し、わたしを含めた読者は第三者として、遠藤周作の姿も視界にとらえながら読むことになります。書いている作者の内的な葛藤の歴史を、行間に読み取ります。それは無信仰な人間にも、不思議に心惹かれる体験でした。
キリスト教や、仏教のような体系化された宗教に興味はなくても、人は心配事があれば解決するよう祈ります。四季の移ろいに、大きな自然の営みと諸行無常の感を抱きます。ほとんど無意識の領域から滲み出てくる心の動きです。
人はなぜ、心の中に人を超えたものを必要とするのか。自ら問いかけても、漠として先が拓けません。ただ、それを「弱さ」と切り捨てるのはあまりにも安易だと思います。
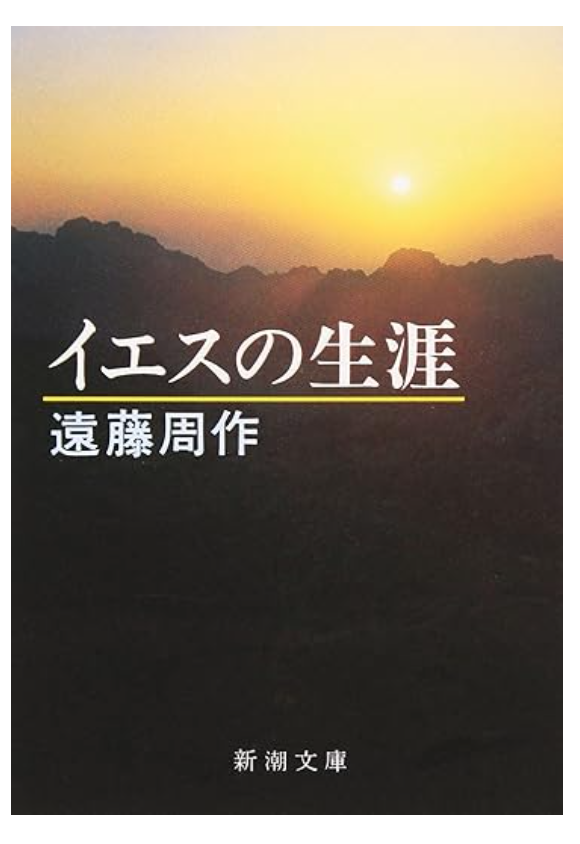 amazon
amazon
