長野の山奥にある祖父母が暮らす家へと、曲がりくねった坂道を父が運転する車は進みます。乗っているのは母と姉、そして小学校5年の<私>。お盆には毎年、その山奥の家におじさんやおばさん、従兄弟たちが集まるのです。
「地球星人」(村田沙耶香、新潮文庫)の導入部は、どこにでもありそうな夏休みの一コマ。小説は<私>の視点で語られるのですが、さて<私>はどんな女の子なのか。
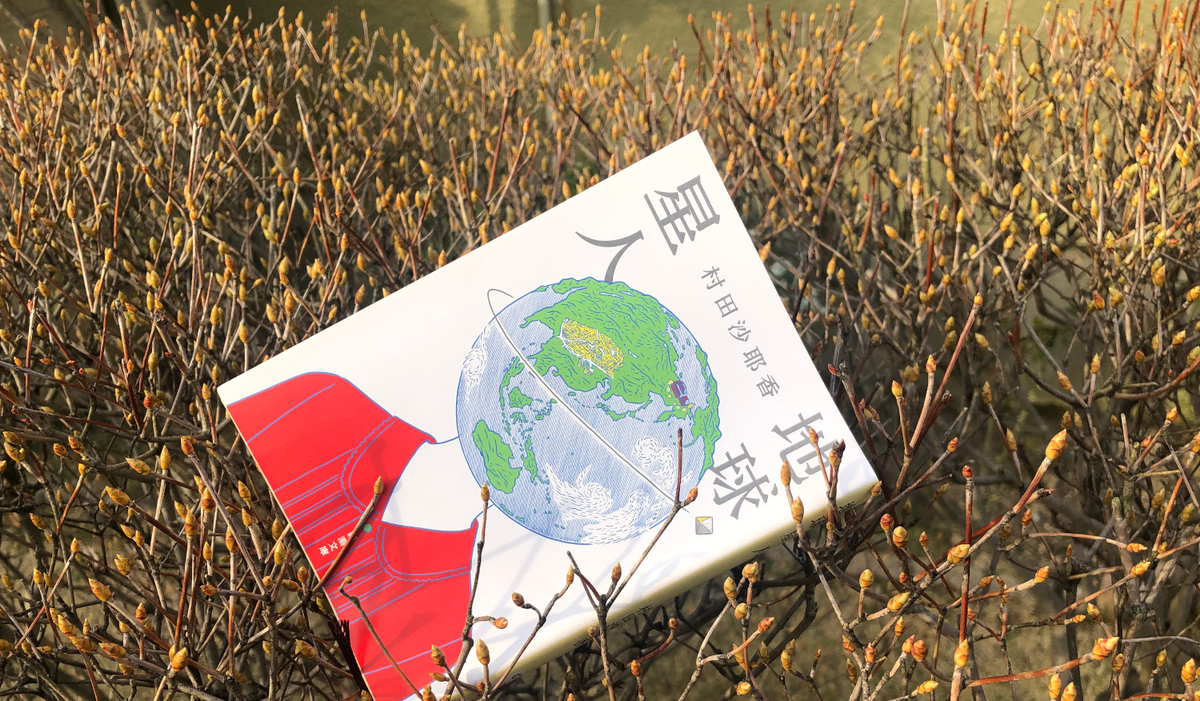
家族には話していないが、私は魔法少女だ。小学校に入った年に駅前のスーパーでピュートと出会った。(ぬいぐるみのピュートは実は、地球を救う任務でやってきたポハピピンポボピア星の魔法警察官で)それ以来、私は魔法少女として地球を守っている。
そんな空想を楽しむのは子供らしいのですが、楽しんでいるのではなく「信じて」いるとしたら...。
作品の前半は、小学生の<私>の物語。母は姉だけをかわいがり、<私>に対しては虐待に近い扱いをしています。しかも塾の若い男性講師から性的な悪戯を受け、母に訴えても取り合ってもらえません。
深読みすれば、空想は過酷な現実を生き延びるための拠り所なのです。だから魔法を使って魔女を打ち倒すことが、リアルでは男の人を殺すことであったかもしれない...。でも子どもの<私>のリアルは、殺人ではなく必死に魔女と戦ったことだけです。
ふと浮かんだのは「本当は怖い○○の童話」という、どこかで耳にしたようなフレーズでした。しかし、読み進むにつれて、物語はそんなありきたりな形容からも易々とはみ出していきます。
子どもの<私>が理解している世界とは、どんな姿なのでしょうか。
ここ(地球)は、肉体で繋がった人間工場だ。私たち子供はいつかこの工場をでて、出荷されていく。
出荷された人間は、オスもメスも、まずはエサを自分の巣に持って帰れるように訓練される。世界の道具になって、他の人間から貨幣をもらい、エサを買う。
やがて、その若い人間たちもつがいになり、巣に籠って子作りをする。
五年生になったばかりのころ、性教育を受けて、私はやっぱりそうだったのかあ、と思った。
.....。
物語の後半は、34歳になった<私>。ここからカニバリズム(人肉食)にまで行き着くぶっ飛び具合は、まあ読んでもらうしかないなあ。
もし本屋大賞受賞作のような、胸熱くなる共感の涙や勇気を小説に求めるなら、お薦めできません。
良識の殻を脱ぐことができないと、この小説(というか、村田さんの他の作品も)は、荒唐無稽か、おぞましいか、あるいはその両方でしょう。しかし村田作品は逃げようのない問いを突きつけてきて、その鋭さはわたしをたじろがせます。
なぜオトコはこうあらねばならないのか、オンナはこうあらねばならないのか。その結果としてのニンゲン社会は、なぜこうなのか。
「いや、それはそういうものだから」とか、「そもそもそのようにしてニンゲンの歴史は積み上がってきたので」とか、論理的な説明を省いた(省くことができる)常識に逃げようとしても、許してもらえません。素朴な子どもの問いかけは、実は怖い。
人間という生き物は、根源的で底の見えない裂け目に対して、宗教や社会常識という便利な目隠しを発明して安寧を得てきました。そのことに気付かされたとき、自分がどんでもない暗闇に放り出されたような気がするのです。
わたしが放り出された暗闇とは実は宇宙で、心細く漂っているのは、地球星人の塵のような良識なのかも。と、読み終えて思いました。

